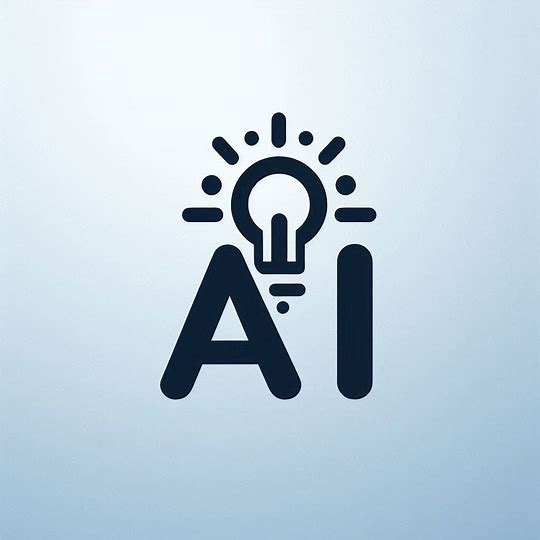災害時の個人でのAIの活用方法5選!命を守る時にAIに聞くことは?

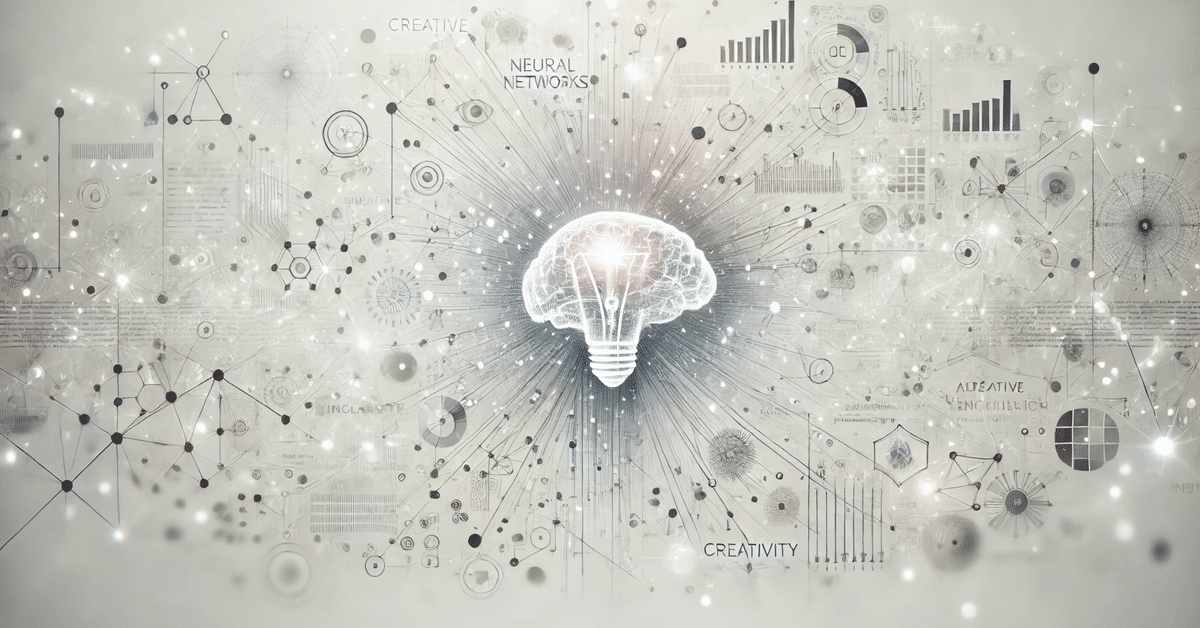
災害時の個人でのAIの活用方法5選!命を守る時にAIに聞くことは?
災害時の個人でのAIの活用方法5選!命を守る時にAIに聞くことは?
1. はじめに
近年、地震や台風、大雨・洪水などの自然災害が増えています。日本は地震大国としても知られ、地震はいつどこで発生しても不思議ではありません。また、台風や大雨による河川の氾濫、大規模停電なども想定されるなか、私たち一人ひとりが「いかに早く正確な情報を入手し、適切な行動を取るか」がとても重要になります。
そこで注目したいのが、AI(人工知能)技術の進歩です。以前は専門家や企業向けのシステムが多かったAIですが、現在ではGoogleアシスタントやSiriなどのAIアシスタント、チャットボット、防災アプリなど、私たち個人が簡単に使えるツールが続々と登場しています。こうした「災害時にAIを活用する」ことで、素早い状況把握や適切な意思決定ができる可能性が高まります。
本記事では、「災害時に個人がAIをどのように活用できるか?」をテーマに、具体的な5つの方法を紹介します。都市部・地方を問わず、幅広い年代の方がすぐに取り入れられる実践的なアイデアです。災害が発生した際、どういった情報をどのように得ればいいのか、どのように周囲と連携すればいいのか——AIツールを上手に使いこなして、「自分や大切な人の命」を守るための一助になれば幸いです。
2. AIの活用方法5選
① AIアシスタントによる緊急情報収集
AIアシスタントとは?
Googleアシスタント、AppleのSiri、AmazonのAlexaなど、音声やテキストで簡単に操作できる「AIアシスタント」が代表的です。災害時にスマートフォンを操作している余裕がない場合でも、音声コマンドを使って手早く情報を得ることができます。
実際にどんな使い方をする?
- 「今いる地域の地震情報を教えて」
→ GoogleアシスタントやSiriに音声で質問すると、気象庁や報道機関が配信する最新情報をもとに回答してくれます。規模や震源地、震度情報を瞬時に得ることが可能です。 - 「避難所はどこ?」
→ AIアシスタントがスマホのGPS機能を利用し、最寄りの公的避難所を地図とともに案内してくれます。自治体のデータベースと連携している場合は、最新の避難場所情報が反映されるケースがあります。
注意点
- 気象情報のソースは公的機関(例:気象庁、地方自治体の防災サイト)を参照しているか必ず確認しましょう。GoogleやAppleなどのAIアシスタントは、通常、気象庁や気象予報会社のAPIなど公的機関・公式情報を参照しています。
- 音声アシスタントの設定言語や位置情報が正しく設定されていないと、誤った地域の情報が提供される恐れがあります。事前に設定を確認しましょう。
② チャットボットやAIアプリを活用した災害対応
防災チャットボットとは?
LINEやその他のSNS上で、災害情報を自動的に受信したり、必要な情報を問い合わせることができるAIチャットボットが存在します。たとえば、LINE公式アカウントで「LINE防災情報」を登録しておくと、自治体やメディアによる最新情報が自動配信されます。また、Yahoo!防災速報アプリなども代表的なAI防災アプリの一種です。
具体的な活用事例
- LINEの防災チャットボット
- 「避難情報を教えて」「最新の台風情報は?」などとメッセージを送るだけで、行政が発表している避難指示や台風の進路予測が返ってきます。
- 友人や家族とのグループチャットにこのボットを追加しておくと、全員が同じ情報を共有しやすくなります。
- Yahoo!防災速報アプリ
- AIが検知した地震や大雨などの緊急情報を、プッシュ通知で素早く受け取れます。
- 気象庁の情報をベースにしているので、信頼度も高いです。
- 「災害時 AIアシスタント」「AI防災アプリ」といったキーワードで検索すると、他にもさまざまなアプリが見つかります。
注意点
- これらのチャットボットやアプリは、気象庁(JMA)や内閣府、防災科学技術研究所などの公的情報を参照していることが多いです。公式のアプリや信用できる開発元のものを選びましょう。
- 災害発生時には通信障害が起きやすいため、オフラインでも最低限の情報が見られるアプリや、事前にキャッシュを残す機能があるツールを活用するとなお安心です。
③ AI画像解析を活用した安全確認
AI画像解析とは?
AIが画像や映像を認識・解析して、被害状況や異常個所を特定する技術です。最近ではドローン映像の解析などでも活用され、自治体や防災関連企業が被災地の全体像を早期に把握する手段として注目されています。
個人レベルでの活用例
- ドローン+AI解析
- 自宅付近に大きな被害が出ているかどうかを、遠隔でドローンを飛ばし撮影。その映像を簡易AI解析ツールにかけることで、「建物の損壊の有無」や「倒壊している電柱の存在」などを検知できます。
- 個人でドローンを所有していなくても、自治体や地域の防災組織がドローンによる被害状況調査を行っている場合があります。そういったサービスで提供される情報をもとに、安全なルートを選択することができます。
- SNS投稿の画像解析
- 大きな災害が起きると、SNS上には膨大な写真や動画が投稿されます。災害関連のAIプラットフォームでは、GPS情報などと紐づけて「どのエリアでどんな被害が起きているのか」を可視化してくれます。
- デマや誤った写真が紛れ込む可能性もあるため、情報源を複数確認することが大切です。
注意点
- ドローンの使用には航空法や自治体の条例など、さまざまな規制があります。飛行禁止エリアや許可の確認など、災害時でもルールを守る必要があります。
- SNSの投稿は真偽が入り混じっている可能性が高いため、公的機関やニュースメディアの情報との突き合わせが必須です。AIも万能ではないため、常に複数の情報源をチェックするようにしましょう。
④ AIによる食料・医療品の管理とアドバイス
どんなサービスがある?
最近は「スマート冷蔵庫」のように、冷蔵庫に内蔵されたAIが賞味期限や在庫管理を行う製品があります。災害時にも自宅に備蓄している食料がどれだけ残っているか、何が足りないかを把握するのはとても重要です。
また、医療分野でも、AIを活用して病状やけがの程度の応急処置方法をアドバイスしてくれるアプリが登場しています。もちろん医師の診断には及びませんが、緊急時のファーストエイドとしては有用です。
具体的な活用例
- スマート冷蔵庫の在庫確認
- AIが冷蔵庫内の食材を読み取り、何がどのくらい残っているか自動で把握。災害が起きる前から設定しておけば、避難の際にすぐ必要な物資が分かるのは便利です。
- スマート冷蔵庫を使っていなくても、スマホアプリで自分が持っている備蓄リストを管理する方法もあります。AIが「そろそろ賞味期限なので、〇〇を買い替えておきましょう」という通知をしてくれるアプリも存在します。
- AI健康アプリでの応急処置アドバイス
- 軽いケガの対処法や、体調不良への対策をチャットボット形式で案内してくれるアプリがあります。たとえば、「この環境下で気をつけるべき病気やケガは?」と質問すると、厚生労働省や日本赤十字社が公表している応急手当ガイドラインなどをもとに、適切な処置方法をテキストで教えてくれる場合があります。
- あくまでAIのアドバイスは参考程度であり、重症の場合はすぐに医療機関へ連絡することが最優先です。
注意点
- スマート冷蔵庫や在庫管理アプリは、メーカーやサービスごとに精度や連携範囲が異なります。購入前・導入前に機能をよく確認しましょう。
- 日本赤十字社や厚生労働省などの公的機関が提供している応急手当や医療情報を参照しているアプリであれば、情報の信頼度が高いです。ただし医師の診断の代わりにはならないので、危険と感じたら早めに119番通報を行ってください。
⑤ AI翻訳を活用した多言語コミュニケーション
多国籍社会における災害対応
日本を訪れる外国人観光客は近年増加傾向にありますし、在住外国人の方も多くいらっしゃいます。災害時には言語の壁を超えたコミュニケーションが必要になるシーンも少なくありません。
どんなツールがある?
- Google翻訳
- スマートフォンでカメラ機能を使い、看板や書類などを写すだけで瞬時に翻訳。インターネット接続が不安定な状況でも、オフライン翻訳パックをダウンロードしておけば利用可能です。
- DeepL翻訳
- ニュアンスの細かい部分も含め比較的自然な翻訳が得られると評判。英語だけでなく、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、韓国語など多言語に対応しています。
- AI文字起こしツール
- 災害時の防災行政無線や緊急放送が聞き取りにくい場合でも、音声をリアルタイムで文字起こししてくれるアプリがあります。日本語がわからない方に対して、翻訳結果を画面で表示できれば安心です。
具体的なシーン
- 避難所で外国人観光客や在住外国人に対し、食事や必要物資の説明をするとき
- 大規模停電でアナウンスが聞き取りづらいときに、AI文字起こし+翻訳を活用して正しい情報を伝達するとき
注意点
- 翻訳AIは年々進歩していますが、専門用語や地名などを誤訳する可能性があります。誤解を避けるためには、シンプルな文章やキーワードでのコミュニケーションが効果的です。
- オフライン翻訳機能を使いたい場合は、事前に必要な言語パックをダウンロードしておきましょう。災害時にはネット接続が途切れる恐れがあるからです。
3. まとめ
AIを活用するメリット
災害は突然やってきます。そのときに、「どこに避難すればいいのか」「何が起きているのか」「周囲の被害状況はどうか」を素早く知ることが重要です。AIを活用することで、個人でも迅速な判断と適切な行動が可能になります。特に、音声アシスタントやチャットボットを通じて手軽に情報を得られたり、多言語対応で外国人観光客や在住外国人ともコミュニケーションできたりする点は大きな利点です。
事前の準備がカギ
ただし、「災害時にAIを使おう!」と思っても、災害発生直後にアプリをインストールするのは通信障害などで難しいケースがあります。事前の準備として以下のステップをおすすめします。
- スマートフォンに防災AIアプリを導入
- 例:Yahoo!防災速報アプリ、NHKニュース・防災アプリなど
- AIアシスタントの設定を確認
- 位置情報や言語設定を最新にしておく
- オフラインで使える翻訳パックや地図データをダウンロード
- 地図アプリや翻訳アプリは事前にデータを入れておくと安心
- 備蓄品リストや応急処置アプリを活用
- AIが期限管理や応急処置をアドバイスしてくれるサービスを確認
今すぐできるアクション提案
- スマホのホーム画面に、よく使う防災AIアプリやAIアシスタントのショートカットを配置する
- 「災害時 AI 活用」「災害時 AIアシスタント」「AI防災アプリ」などのキーワードで検索し、使いやすそうなツールをいくつか比較してみる
- 友人や家族と共有して、グループチャットに防災チャットボットを追加しておく
災害はいつ起こるか分かりません。だからこそ、普段からの備えが大切です。AIの力を借りて、いざというときの迅速な判断と行動につなげましょう。被害を最小限に抑えるためにも、ぜひ今すぐスマホに防災AIアプリを入れてみてください!
参考リンク(公式情報・公的機関)
- 気象庁(JMA)
- 最新の地震・津波情報、台風情報、大雨警報などを確認できます。
- 内閣府 防災情報
- 防災対策や避難についてのガイドラインがまとめられています。
- Yahoo!防災速報
- アプリのダウンロードページ。地震や大雨などの速報を受け取れます。
- NHKニュース・防災アプリ
- NHKが提供する防災アプリ。災害時のテレビニュースをスマホでも確認できます。
生成AIを活用して作成したマンガ、書籍と執筆した本(Kindle Unlimited ユーザーは無料で購読できます)是非、手に取ってみてもらえると。
40代から始めるキャリア・リスキリング予備校の教科書: 今からでも間に合う!人生100年時代の最強転身メソッドamzn.to
499円(2025年01月18日 06:49時点 詳しくはこちら)
500円(2024年12月05日 05:46時点 詳しくはこちら)
499円(2024年11月23日 06:10時点 詳しくはこちら)
マンガでわかる成功の方程式: キャリアと人生のバランスamzn.to
499円(2024年11月15日 06:06時点 詳しくはこちら)
399円(2025年01月30日 06:14時点 詳しくはこちら)
※出版できないなどの理由で法人、個人での電子書籍(マンガを交えるなど)、紙書籍(Kindle)の出版を行いたい方は、こちらまでご相談ください。お手伝いをいたします。
これからの生成AIを使いこなすためのスキルであるプロンプトの学習のための無料セミナーはこちら
AIに関する無料相談のご案内(会社名AIdeasHD LLC)
生成AIを活用したさまざまな日常業務の改善による生産性向上を提案しております。
ご興味がある方は
こちら
もしくは
aideashd@gmail.comからご相談ください。
無料でご相談いただけます。
著者紹介(橋本 正人)
著者は、AIの活用で企業業務(究極の生産性を追求した株式会社キーエンスでは営業、営業企画、生産管理、デジタルでの究極の生産性を追求したセールスフォースではCX、DXの専門家、執行役員営業本部長)に従事してきており、その後、独立しプロンプトの技術であるプロンプトエンジニアを取得し、生成AIを活用したさまざまな日常業務の改善による生産性向上を提案しております。
AIのことをメインにしてますが、AIにはできない想像力豊かなアイデアで独特な絵を描くちょっと障がいがあるレンくん(保育園から書いていてちょっと有名?今は1年生でも展示会に出品されるなどでちょっと有名?)が書いたほのぼのとした作品をYou Tubeで公開しています。
よかったらみてみてください!
ほのぼの画家Renくん
https://www.youtube.com/@HeartwarmingPainterRen